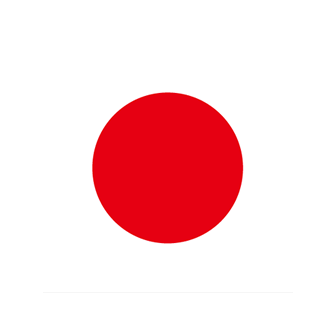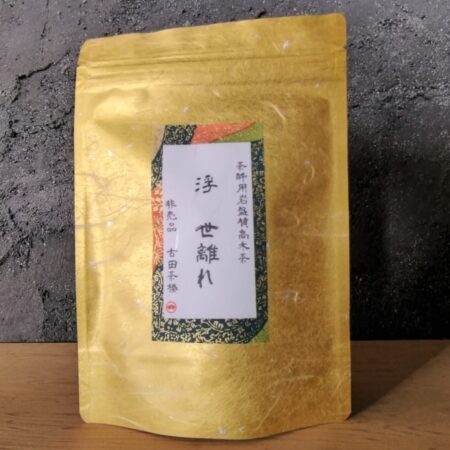産地 池尾(京都府 宇治 喜撰山)
年間収穫回数 初茶のみ
収穫方法 一芯二葉 手摘み
揉捻方法 手揉み
乾燥方法 備長炭乾燥
半発酵茶
「標高が高く痩せた土地からは、香りに優れたお茶が採れる。
標高が低く水はけの良い土地からは、味に優れたお茶が採れる。」と言われます。
宇治で最も標高の高い茶産地は、喜撰山の池尾でした。霧が立つこの地は、痩せた神の赤土です。
わざわざ明恵上人がこの地を選び、茶の種を植えてくださったのはそんな背景からでしょうか。池尾には、芥川龍之介の出世作「鼻」の舞台になったお寺が現存します。そして喜撰法師が都を捨ててまで求めた環境が、肌で感じられます。「臥龍仕立」(がりゅうしたて)と呼ばれる、茶樹を連ねて龍が横たわっているような形に仕立てるのが池尾の伝統でした。2012年から始めた茶山再生も終わり、手摘み型臥龍仕立てが池尾には有ります。文化や芸術が隠れている池尾は、特別な茶山と感じます。扱うには、敬意と覚悟が必要と思いました。池尾茶に相応しく手摘み・手揉み・備長炭乾燥としました。
この素材の魅力を、最大限に引き出せる製茶方法は何だろう?と白茶、紅茶、緑茶・・・様々なお茶へと試行錯誤しました。結果は、どれも魅了的で順位がつけられませんでした。なので様々な製茶の試飲に付き合ってくれた妻が、一番喜んでくれた香りの製法で仕立てました。「女が喜んで嬉しいと書く」と知りました。なので嬉茶と命名されました。感謝してます。
嗜好品の為、飲み方に決まりはございません。
【参考例】
二人分:茶葉半袋 熱湯150cc抽出時間は3分
2煎目から抽出時間を伸ばし、7煎は十分お楽しみ頂けます。